[episode10]あの日と同じ雪が降る(後編)
- mam

- 2025年7月23日
- 読了時間: 3分
※先に前編をお読みください。
通夜には間に合わなかった。
斎場の名を聞いたのは、晴一の娘からの一本の電話だった。
どこか機械的な声で、でもその奥に涙が滲んでいた。
──父が、亡くなりました。
──眠ったまま、朝を迎えられませんでした。
言葉を返せなかった。
直哉はただ、スマートフォンを握ったまま、冷たい廊下に立ち尽くした。
最後に会ったのは、ほんの数日前だったのに。
いや──本当に、会ったのだろうか。
あれは都合の良い夢だったのか。
それとも、あいつが最期に見せてくれた“思い出”だったのか。
けれど確かに、雪が降っていた。
河原のベンチに並んで座り、どちらからともなく口を開いた。
言いたかったことを、ようやく伝えられた。
あいつの声も横顔も、たしかに胸の奥に残っていた。
* * *
葬儀が終わったあと、直哉はふらりと河原に立ち寄った。
薄曇りの空から、季節外れの雪がちらついていた。
あの日と、同じ雪。
ベンチは変わらず、そこにあった。
けれど隣に座るべき人物は、もうどこにもいなかった。
「……会えたのかな、ちゃんと」
独り言のように呟いて、直哉はそっと目を閉じた。
たった一晩の夢。
それだけで、確かに心の重しが少しだけ軽くなっていた。
雪が舞う中、風に吹かれて一枚の写真が足元に舞い降りる。
拾い上げると、それは晴一が撮ったらしい、かつての河原の風景だった。
その隅に、小さく映る二人の若い影。
直哉はふっと息を吐いて笑った。
「やっぱり、おまえはズルいな……最後まで、俺に何も言わせねぇで」
でも、ありがとう。
またな。
河原の雪が、静かに彼の足元を白く染めていく。
* * *
その夜。
月の上にある静かな部屋。
小さな食卓に、ふたり分の湯気が立つ。
スープの香り。柔らかなパン。焼いた根菜の甘み。
「……今回は、特につらかったな」
モモが湯気の奥で言う。
アオはパンをちぎりながら、静かに頷いた。
「でも……最後に会えてよかったと思うよ」
しばし沈黙が流れた。
「なあ、アオ」
モモが湯飲みを口に運びながら尋ねる。
「もし俺が、そういう立場になったら……おまえは現れてくれるか?夢ん中。」
アオは一瞬、手を止めた。
それから、やわらかく笑って、こう言った。
「ううん。行かないよ」
「なんでだよ」
「だって……モモの最期の夢に、僕はいなくていいでしょ。きっとモモのいちばん幸せな思い出に、僕はいない。もちろん、任務としては行くかもしれないけど」
モモは少し黙ってから、口元をゆるめた。
「……そうかもしれねぇな?でも、おまえの最期の夢には俺が出てやってもいいぜ」
「うん、そうだね。そっちの方がしっくりくる」
ふたりの会話は、それきり特別な言葉を交わすことなく、静かに流れていった。
皿が空になり、湯気が消え、夜が深くなる。
月の森には、やわらかな光と、ふたりの気配だけが満ちていた。
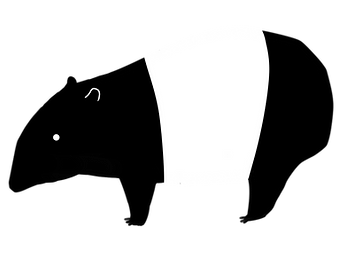
![[episode09]あの日と同じ雪が降る(前編)](https://static.wixstatic.com/media/114c79_fd8a67c44a544e7b95648b11be7c1771~mv2.png/v1/fill/w_940,h_788,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_fd8a67c44a544e7b95648b11be7c1771~mv2.png)







![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_298,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)
![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_74,h_62,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)





コメント