[episode09]あの日と同じ雪が降る(前編)
- mam

- 2025年7月21日
- 読了時間: 4分
夢の世界に降り立つと、アオはすぐに空気の重たさを感じた。季節は冬。川べりの河原。枯れ草が風に揺れて、遠くからは夕暮れの電車の音がかすかに聞こえる。
「誰もいないみたいだな」
モモがバクの姿から人間の姿へと変わる。冷えた空気を一度深く吸い込み、ゆっくりと吐き出した。
そのとき、小さな声が聞こえた。
「……ここじゃなかったんだな」
アオが振り向くと、ベンチの端に、ひとりの中年男──有馬晴一が座っていた。
60代前半。白髪が目立ち始めた頭に、分厚いコート。手にはカメラを持っている。
だが、その目は、ずっとある一点を探しているようだった。
「この河原、よくふたりで来てた。夏井と。ガキみたいに川に石投げて……寒くても、雪でも、くだらない話してさ」
晴一の声には苦笑が混じっていた。
「でも、この間のケンカで──もう、会わないって言っちまった。……向こうも、本気で怒ってる顔だった」
ふたりは、ある同窓会の話題で言い争ったのだという。
晴一が昔の旧友の悪口を笑って話したのに対し、夏井が「それは言い過ぎだ」と真顔で返してきた。
些細な意見の相違だった。けれど、長年の関係だからこそ、逆に“深く刺さる”一言があった。
「たぶん、俺は……あいつが、俺の言葉に傷ついた顔を、見たくなかったんだと思う。だから、先に怒ったふりして突き放した」
アオは、静かに尋ねた。
「会いたくない?」
「……会いたくない。謝る気もない」
晴一はうつむいたまま言った。
「でも、あいつが先に『ごめん』って言ってくれるなら……」
そこまで言って、言葉が詰まる。
「前みたいに、またくだらない話がしたい。孫の写真を送り合って、朝ドラの感想語って、天気の話して……でも、もう、あいつに“俺は悪くなかった”って言い訳もできない」
風が吹いて、河原の空気が少しだけ揺れる。
ふと、背後から声がした。
「おまえさ、ほんと、そういうとこだよな」
アオが振り返ると、そこには夏井直哉が立っていた。
ニット帽をかぶり、分厚い手袋をした手に、使い古した手帳を持っている。
「夢の中か……なんでこんなとこにいるんだ、俺」
直哉は自分の足元を見下ろしたあと、苦笑した。
「晴一のこと、ふと思い出したからかもな。ずっと写真送ってこねえから、ついにスマホ壊れたかって思ってたけど」
晴一は、ベンチに座ったまま、ゆっくりと顔を上げた。
「直哉……」
「おまえな、同窓会のことで怒るのはいいけど、孫の話くらい送ってこいよ。じいじ自慢したくてウズウズしてたくせに」
声が震えていた。
「俺さ、なんであのとき怒ったかっていうと……おまえが俺以外の“昔の誰か”にばっか目ぇ向けてた気がして、腹立ったんだよ」
ぽつぽつと、雪が降りはじめた。
「おまえ、俺のことだけは忘れねぇって思ってたのに。自信、なくなった」
晴一は、唇を震わせながら言った。
「俺も……あのとき、そう思ってた。『俺のことだけは分かってくれる』って。だから、期待しすぎて、勝手に傷ついて、勝手に怒った」
静かに雪が積もっていく。アオとモモは、ふたりの傍から離れ、そっと距離を取って見守っていた。
「……これが最後になるかもしれない」
晴一が言った。
「現実で、会える保証はないから」
直哉は一瞬だけ黙り、それからベンチに腰を下ろした。
「じゃあ、夢でくらい仲直りしとくか」
ふたりの肩が触れるか触れないかの距離。
「あとでさ、目ぇ覚めたら、文句でも何でも言ってこいよ。また同じこと言い合ってやる」
「うん」
それだけで、長年の沈黙が、少しだけほどけた。
遠くで電車が走る音がした。
夢の中の河原を、雪がゆっくりと包んでいく。
────
──でも、目が覚めることはなかった。
それを知っていた。
晴一は、夢の奥で、どこかでそのことを感じ取っていた。
(きっともう、朝は来ないんだろう)
それでも、夢での再会に満たされていた。
直哉の顔を見て、声を聞いて、怒っていた気持ちも、寂しさも、すべてが胸の奥で溶けていくのを感じた。
(本当は、会えてよかったって……ちゃんと伝えたかったな)
でももう十分だ。
ありがとう、と心の中で呟いて、雪の音とともに、その姿は静かにほどけていった。
(続く)
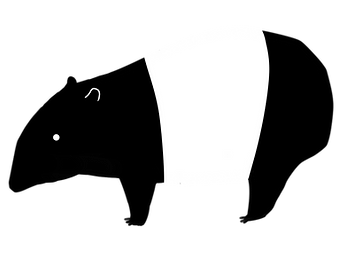
![[episode08]あの夏の背に触れて](https://static.wixstatic.com/media/114c79_b01f79331e1443c6b469f9a13089f97b~mv2.png/v1/fill/w_940,h_788,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_b01f79331e1443c6b469f9a13089f97b~mv2.png)
![[episode07]月のキッチンにて](https://static.wixstatic.com/media/114c79_2fcbff6423f9408c8fa5222edeaf9b11~mv2.png/v1/fill/w_940,h_788,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_2fcbff6423f9408c8fa5222edeaf9b11~mv2.png)
![[episode06]春雷の夜、手を取って](https://static.wixstatic.com/media/114c79_a611bafae7d249a3943b4dc66e8d85ce~mv2.png/v1/fill/w_940,h_788,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_a611bafae7d249a3943b4dc66e8d85ce~mv2.png)







![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_298,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)
![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_74,h_62,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)





コメント