[episode06]春雷の夜、手を取って
- mam

- 2025年7月14日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年7月21日
夢の劇場には、誰もいなかった。
カーテンは閉ざされ、照明は落ち、舞台袖にすら人の気配はない。にもかかわらず、その中央にひとり、男が立っていた。背筋を伸ばし、舞台を踏みしめるように。
彼の名は真澄(ますみ)。
30代半ば、舞台俳優として20年近いキャリアを持つベテラン。
かつては“若き天才”と呼ばれ、劇団の看板として数々の難役を演じてきた。
だが今、彼の目には迷いが浮かんでいた。
「誰か……この台詞、受け取ってくれよ……」
手には、ぼろぼろになった脚本。
それは彼が最後に演じた舞台『春雷』のものだった。公演中、照明トラブルで起きた事故により、真澄は舞台から転落。そのまま意識を取り戻さず、病院のベッドで静かに命の灯が消えかけている。
夢の中でも、彼はまだ“演じて”いた。
アオとモモは観客席の最前列から、その姿をじっと見つめている。
「……声が届かないんだな」
モモの耳がぴくりと動く。
「この人、本番の時と全然違う」
アオが呟く。「演じてるのに、どこか寂しそう」
舞台の中央に立つ真澄が、ふと顔を上げた。
その目は、誰かを探すように暗がりを見つめていた。
彼には、かつて相棒がいた。
律(りつ)──同じ劇団で出会い、共に多くの舞台に立った男。
真澄より少し年下で、柔らかな声と冷静な演技が魅力の俳優だった。
互いに惹かれていた。
だが、それを“言葉”にすることはなかった。
舞台上の役柄にすべてを託し、現実では触れられないまま、律は突然劇団を辞めて姿を消した。
そして真澄は、律が最後に残した舞台『春雷』を、彼なしで演じた。
──初日のキスシーン。
脚本にはなかった、あの一瞬。
律が自ら台本を越えて、真澄に唇を重ねた。
「……あれは、演技じゃなかった。あいつの、本気だった」
その記憶だけが、真澄の“いちばん幸せだった瞬間”として、夢に焼きついていた。
アオとモモの背後、舞台の照明がにじむように灯る。
「始まるぞ」
モモが低く言った。
照明が上がり、舞台の景色が一変する。初日の舞台。
観客は満員、拍手のざわめきがかすかに聞こえてくる。だが、夢の中では観客の顔は霞んでいて、ただ一人、舞台袖から現れる男の姿だけがはっきりしていた。
律だった。
「……真澄。おまえのセリフ、俺は今でも覚えてる」
その声に、真澄の目が大きく見開かれる。
「律……」
かすれた声が漏れる。
「もう一度だけ、ここで言わせてくれ」
律が一歩、舞台に踏み出す。
「演技でも夢でも構わない。おまえに伝えたい──『好きだった』って」
真澄の手から、脚本がふわりと落ちた。
セリフではなく、自分の言葉を選ぶ。
「俺も……おまえがいたから、役に生きられた。全部、演技じゃなかった。……好きだった」
照明がふたりを包み込む。
舞台の上で、静かに唇が重なる。
その瞬間、観客席のアオが小さく呟く。
「……やっと、幕が下りたんだね」
静かな拍手が、夢の中に響く。
誰もいないはずの客席、無数の“見届け人”たちが、ふたりの舞台に手を叩いているようだった。
そして、舞台の光がゆっくりとフェードアウトする。
その姿は、やがて春の光にほどけるように消えていった。
舞台の中央には、静けさが戻った。
しばらく沈黙ののち、客席の最前列から、アオがぽつりと呟いた。
「……綺麗だったね」
モモは隣で足を組み替えながら、気怠げに笑う。
「愛だよ、愛。舞台の上でも、本音を隠すのは骨が折れるもんさ」
「それでも、伝えたい言葉があるって……素敵だと思う」
アオの目にはまだ、消えていった光の残像が映っていた。
「じゃあ、次の夢に行こうか」
モモが立ち上がり、伸びをする。
「うん。……また誰かの、大切な記憶に会えるといいな」
ふたりの足音が、静まり返った劇場を離れていく。
月の光がそっと舞台を照らしていた。
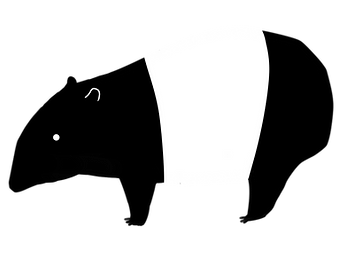
![[episode05]ラジオの向こうの君](https://static.wixstatic.com/media/114c79_b49184e00eb8420cae05498b5899f288~mv2.png/v1/fill/w_940,h_788,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_b49184e00eb8420cae05498b5899f288~mv2.png)
![[episode04]繕いの部屋](https://static.wixstatic.com/media/114c79_b8117d5e578b4b8b8f4bab4e0d74e162~mv2.png/v1/fill/w_940,h_788,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_b8117d5e578b4b8b8f4bab4e0d74e162~mv2.png)
![[episode03]時計仕掛けの約束](https://static.wixstatic.com/media/114c79_3310883a1b574da7a311e4c0c7c26187~mv2.png/v1/fill/w_940,h_788,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_3310883a1b574da7a311e4c0c7c26187~mv2.png)







![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_298,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)
![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_74,h_62,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)





コメント