[episode07]月のキッチンにて
- mam

- 2025年7月15日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年7月21日
月の空に、金色の光がさしていた。 窓の外に広がるのは、静かなクレーターと銀色の砂丘。風もなく、音もなく、ただ光だけが優しく降りてくる。
アオの住まいは、月の丘の上に建っている。こぢんまりとした石造りの小屋には、薪ストーブとベッド、書きかけの手紙と、本棚がひとつ。それから──台所がある。
冷蔵庫を開けると、その中は緑色一色。月菜が保管してある。
月菜とは、地上で言えばカブの葉っぱのような形状をしている青菜で、栄養価が高い。アオはこれを主食として食べている。健康上は問題なく栄養を摂れているが、正直言って味を楽しむものではない。
「モモ、月菜のサラダでいい?」
「…他になにかできるのか?」 ソファで横になっていたモモが、片目だけ開けて答える。アオは料理というものをほとんど知らない。月菜以外にも、きのこなど乾燥して保存できる食材は月にもいくつかある。キッチンにも火を使える設備は揃っているが、食事というものにさほど興味がないため「あらう」「切る」「ゆがく」くらいしかしないのである。
大きなバクの姿から、すらりとした大人の男の姿へと、もこもこと変身する。
「どうせ生きるなら“うまいもん”食って生きろって…地上じゃあ、言うんだぜ」 モモはアオの肩をポンと叩いた。
「うまいもんって…たとえば?」
「いいか、アオ。食べることは、記憶とつながってるんだぜ。これはお前さんも知っておいて損はないんじゃないか?たとえば──あったかいスープとか、どうだ」
アオはふと立ち止まり、目を伏せた。
「……月菜で?どうやって?」
「よし。俺が教えてやるよ。」
モモは立ち上がり、袖をまくった。 火をくべ、鍋を出し、月菜と乾いたきのこを刻む。棚の奥から取り出したのは、地上で拾ってきたという干したニンニクと塩の瓶。アオは目を見張った。
「えっ、それ、地球の……」
「こないだ、ひとりで降りたときにちょっと失敬してきた」
「いつのまにそんな… あ、散歩ってそういう…?」
時折ひとりで出掛けていたことを思い出した。呆れた表情のあと、アオの頬はゆるんだ。
鍋に水を張り、じっくりコトコトと煮込んでいく。 月菜の青ときのこの茶、ニンニクの香りが漂い始め、アオの耳がぴくりと揺れた。
「……なんか、すごくいい匂い」
「だろ? 月にあるもんでも、工夫すればごちそうになる。あと大事なのは、“誰と食べるか”だ」
木のスプーンで一口、味をみるモモ。満足げにうなずくと、アオの前に小さな皿を差し出した。
「ほら、できたぞ。月菜ときのこのポタージュ──“モモ風”。…これにミルクを入れたらもっとうまいんだが」
湯気の立つ皿を両手で受け取ったアオは、そっとスプーンをすくい、口に運ぶ。
やさしい塩気。舌に残るコク。ふわっと香る、知らないはずの懐かしい匂い。
「……なんか、胸があったかくなる」
「それが“うまい”ってことさ」
モモは壁に寄りかかって、にっと笑う。
アオはもう一口、静かにスープをすくう。窓の外の銀の丘が、ほんの少しだけ金色を帯びて揺れたように見えた。
「ねえ、モモ」 アオが口を開いた。
「いつか、僕も地上の味をもっと知ることってできるのかな」
「…できるさ。おまえが望むなら、いくらでも。」
「そっか。……そしたら、僕も誰かにごちそうできるようになりたいな。夢の中じゃなくて」
「へえ」 モモは目を細めて、照れたように笑った。
「そんときゃ、最初の一人は俺で頼むぜ、アオ」
「うん。約束」
いつ叶えられるかもわからない約束でも、かまわない。いつかを語り合う相手なんて今までいなかったのだから。
湯気の立つ月のキッチンで、ふたりは互いにそう思っていた。
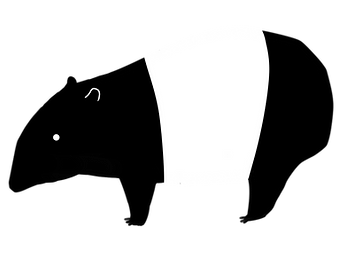
![[episode06]春雷の夜、手を取って](https://static.wixstatic.com/media/114c79_a611bafae7d249a3943b4dc66e8d85ce~mv2.png/v1/fill/w_940,h_788,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_a611bafae7d249a3943b4dc66e8d85ce~mv2.png)
![[episode05]ラジオの向こうの君](https://static.wixstatic.com/media/114c79_b49184e00eb8420cae05498b5899f288~mv2.png/v1/fill/w_940,h_788,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_b49184e00eb8420cae05498b5899f288~mv2.png)
![[episode04]繕いの部屋](https://static.wixstatic.com/media/114c79_b8117d5e578b4b8b8f4bab4e0d74e162~mv2.png/v1/fill/w_940,h_788,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_b8117d5e578b4b8b8f4bab4e0d74e162~mv2.png)







![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_298,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)
![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_74,h_62,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)





コメント