[episode11]君にだけ、触れたかった
- mam

- 2025年7月25日
- 読了時間: 5分
白い天井。規則的な電子音。薬剤の匂い。
それが、彼の今いる世界だった。
名は遥斗(はると)。三十歳、都内の不動産会社で働く営業職。
職場で倒れ、救急搬送されたのが三日前。意識は未だ戻っていない。
けれどその精神は、夢のような風景の中をさまよっていた。
夢の中には、弟がいた。
瑞稀(みずき)。八つ下の弟。
子どもの頃から、よく笑う素直な性格で、兄によく懐いている弟だった。
大人になった今も、ふたりはたびたび会っていた。遥斗が就職し、実家を出て一人暮らしを始めてからも、兄弟だけで食事をする機会も多い。他愛もない連絡を日々とりあっていて、それは瑞稀が大学生になってからも変わらなかった。
けれど──。
夢のなかの瑞稀は、静かな午後の図書館で本を読んでいた。
光に縁取られた頬のやわらかな輪郭、伏せた睫毛、カップの中のぬるくなった紅茶。
それは、遥斗が“いちばん大切にしていた時間”だった。
アオとモモは、その様子を見守っていた。
「静かだな……でも、気配が濃い」
モモの耳がわずかに動く。
「うん。彼の中で、ずっとくすぶってた感情のせいかも」
アオはそう言って、そっと図書館の空気に目を細めた。
──誰にも、渡したくなかった。
その思いが、遥斗の胸に深く根を張っていた。
兄弟という関係でなければ、こんなにも自然に、隣に座ることなんてできなかった。
誰よりもそばにいたいと思った。 でも、口にしてしまったら、すべてが壊れてしまう気がした。
だから恋人もつくらなかった。他人の影を見せることで、瑞稀は距離をとるだろう。それが怖かった。 自分でも理由がわからないふりをし続けていたけれど──本当は、ずっとひとりを選んできた。
──あいつの隣は、他の誰のものでもないって、信じたかった。
夢の景色が、そっと変わる。
春先の公園。桜が咲いていた。
並んで腰掛けたふたりの足元を、風が撫でていく。
『ねえ、兄ちゃんって……彼女、いないの?』
『いないよ』
『マジで? こんなにかっこいいのに』
それは、瑞稀の素直な感想。あどけない尊敬と憧れだ。
けれどその言葉は、遥斗の胸の奥を強く叩いた。
──だって、俺はお前しか見ていない。
『そろそろさ、誰かと結婚とか考えないの?そういうことがあってもいい歳でしょ』
『……考えてない』
弟が眉を下げて笑う。
『もしかして、ずっと俺とふたりで遊んでるつもり?』
それはただの冗談。
けれど、その一言に、遥斗は息をのんだ。
──そうだ、そうできたらよかった。
そんな願い、抱いてはいけない。
『……いや。おまえに彼女ができるまでならいいだろ。でももしそうなったら…寂しくなるな』
苦し紛れの言葉だった。 でも、瑞稀は笑ってうなずいた。
『じゃあ、もうちょっと先でいいや。兄ちゃん、結構寂しがりやだよな。会社のつきあいとか友達との約束とかもあるだろうに、俺ばっかり誘ってさ。』
それが、最後の会話だった。
数日後、遥斗は過労が祟って職場で倒れ、意識が戻らない状態になった。
その間、遥斗は夢のなかでずっと瑞稀の姿を探していた。
アオがそっと呟いた。
「ここまで強く誰かを想っても、言葉にできなかったんだね」
「…兄弟ってのは、距離が近すぎて難しい」
モモが息を吐く。「だけど……それでも、ただひとりの名前を呼んだんだ」
次の瞬間。
夢の風景の隙間から、現実の“声”が差し込んできた。
「兄ちゃん……!」
その声に、遥斗の意識がゆれる。
──瑞稀?
現実の病室。うわごとで呼ばれた名前を辿って、瑞稀が駆けつけてきた。 取り乱したまま、遥斗の手を握る。
そのときだった。
遥斗の唇がわずかに動いた。
「……瑞稀、行くな……」
「おまえに彼女なんて、できてほしくない……」
「そばにいたい……おまえだけが、そばにいてくれたら……」
「……ずっと、触れたかった」
浅い呼吸とともに掠れた声で紡がれる言葉に、瑞稀は息を飲んだ。
思わず顔を伏せ、唇を噛みしめる。
混乱と、戸惑いと、それでも心のどこかで確かに感じていた“気配”── ずっと隣にいた兄の視線や、沈黙の重さ、他の誰にも向けられなかった優しさの理由。
全部が、いま繋がった気がした。
「……兄ちゃん」
震える声で、彼は応える。
「どうして……恋人とか、ずっといなかったのか、わかった気がするよ。兄ちゃん。なぁ…ちゃんと目、覚まして。俺、ちゃんと兄ちゃんから聞きたいこと、言いたいことだって…いっぱいある」
遥斗は、夢の中でその声に向かって手を伸ばした。
その瞬間──夢の光が、ぱちりと砕けた。
閉ざされていた意識が晴れた。目を覚ましたのだった。
*
アオとモモは、静かな月の食卓に並んで座っていた。
「まさか生き延びる…なんてね」
アオがぽつりと呟く。
「あれは奇跡みたいなもんだろ。あそこから目覚めるやつ、滅多にいないわけだし」
モモはカップを傾け、ふぅとため息を吐いた。
「うん。でも、よかった」
「ん?」
「彼……まだ、あの子に言えてない言葉があるみたいだったから」
「ああ……『触れたかった』って?」
アオが頷くと、モモは軽く笑った。
「ゆっくり、ちゃんと向き合えば、伝えられるだろ。」
「そうだね」
***
そして、遥斗と瑞稀の“その後”──
病室の静けさのなかで、遥斗はそっと瑞稀の手を握り返す。 ふたりの間に流れる空気は、きっと以前と同じではない。
だけど、それまでの関係が崩れたわけでもない。
隠していた想いを、少しずつ照らすように── また、新しい関係を紡いでいくのだろう。
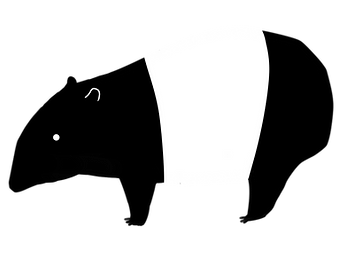
![[episode10]あの日と同じ雪が降る(後編)](https://static.wixstatic.com/media/114c79_f30ed1f9374b425d8360c53b1d899cf9~mv2.png/v1/fill/w_940,h_788,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_f30ed1f9374b425d8360c53b1d899cf9~mv2.png)







![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_298,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)
![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_74,h_62,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)





コメント