[episode13]ふたりの部屋に灯りはともる
- mam

- 2025年7月29日
- 読了時間: 6分
更新日:2025年7月31日
誰よりも近くて、誰よりも遠い。
互いに親にも話せない関係を十年続けていると、その事実は愛というより、風景に近くなる。
「なあ、今日こそちゃんと見合いはやらねぇって言ってくれたか?」
終電帰りの夜、濡れた傘を玄関に並べながら、光希(こうき)が聞いた。
「…いや。…言えるわけないだろ。あんな雰囲気で」
湊(みなと)は苦く笑い、リビングのソファにどさりと沈んだ。
ふたりは今年で三十を越えた。大学時代にサークルで出会い、意気投合した。ふたりでいるのがとにかく楽しく、卒業後も一緒にいた。どうせならと部屋を借り、ルームシェアするかたちで生活を共有し、気がつけば十年が過ぎていた。
いわゆる甘い関係というよりは、一緒に生きるならこいつ、と心の底から思える。もし前世というものがあれば生涯ともにした存在だったのではと思えるほど、しっくりくる相手。そこに第三者の存在が現れるような余地はない。
大学時代こそ「恋人同士」という呼び方をとって照れ笑っていたが、十年の時間を超えて、ただの親友でも恋人でもない、すでに家族と呼べるほどに成熟した。
それでも互いの実家には、ただの“仲のいい男友達とのルームシェア”とだけ伝えてある。
両親に嫌われたくない、悲しませたくない、失望されたくない── その感情は、嘘よりずっと重かった。
互いの両親はどちらも善良で、真っ直ぐな人たちだ。「ふたりでいるのも楽しそうだけど、それならそれぞれに家族を増やしたほうが楽しいでしょう」 悪意なく、ただただ自分たちの行く末を慮ってのことだからこそ、ずっと言えなかった。
こいつとふたりで一生を過ごしたい。
じじいになって最期を迎えるとの時も、隣にいるのはこいつが良い。
それなのに、そんな気持ちを抱えてどこかの女性と誓うことなどできようはずがない。
光希は冷蔵庫から缶ビールを二つ取り出し、湊に放り投げた。プシュ、と乾いた音がして、ふたりは無言のまま口をつけた。
しばらくテレビの音だけが響いていた。
光希がそっと、口を開いた。
「……俺さ、半年くらい前から、ずっと考えてたんだ」
「何を」
「このまま続けてて、俺たち……大丈夫なのかなって」
湊が静かに缶を置いた。
「俺もだよ」
「え……?」
「ずっと思ってた。いつかどちらかが、限界を迎えるんじゃないかって。誰かにバレるとか、じゃなくて……もう嘘をつき続けることに、心が壊れちまうんじゃないかって」
光希は目を見開いた。
「それを……どうして、今まで……」
「おまえが俺より強いと思ってたから」
「俺だって、同じ理由で言えなかったよ。泣き言いってんじゃねえって言われそうで……」
ふたりは思わず、吹き出した。泣きそうな笑いだった。
こんなに苦しいのに、こんなに好きなのに。 どちらかが言い出したら終わるような予感がして、口にできなかった。
「だからさ……湊」
「ん」
「もし、もう全部終わりにしたいってんなら……、俺も一緒に行くよ」
湊は一瞬だけ、動きを止めて、光希の目を真っ直ぐに見た。
「──おまえと生きられないなら、残りの人生なんていらない」
その言葉が、なによりも優しくて、なによりも重かった。
ふたりは、そっと手を取り合った。
同じ日、同じ夜、同じ決意。
そうして、眠るように薬を口にした。
***
──夢の中は、都会の片隅だった。
雨上がりのアスファルト。自販機の明かり。通い慣れた帰り道。 そのすべてに、二人だけの記憶が詰まっていた。
ふたりの時間は、この夢の風景に滲み込んでいた。
そこに、アオとモモが降り立った。
「ここが……ふたりの夢?」
アオが見上げる空は、どこまでも曇っていた。
モモはふたりの姿を目にとめ、眉をひそめた。
「……こいつら、心中だ。ほぼ同時に薬を飲んでるんだな。どっちも夢主だ」
「じゃあ、もう……」
「いや、魂が不安定になってる。まだ間に合うかもしれない。ただ──」
モモの声がワントーン低くなった。
「こいつら、死にたかったわけじゃねえんだろうな。“このままじゃいけない”って、それだけで……眠るように逃げたんだ」
アオはふたりを見た。 光希は夢の中で煙草を吸っていた。湊はその隣で缶コーヒーを持っていた。言葉はない。ただ、互いの存在が側にあるという確信だけがあった。
「……ふたりとも、すごく静かだね。まるで、何かを諦めたような」
アオの小さな声でつぶやいた。重く静かな空気が流れる。
しばらく黙っていたモモが、口を開いた。
「アオ、おまえはどうしたい」
「え?」
「いつもは“幸せな記憶”を探して、送り届けてやるのが役目だ。でもこいつらはまだ、終わってねえ。ここで終わらせることが唯一の選択肢だと思いこんでいるだけだ」
「…ええと、じゃあ、…なにかの間違いだった、て送り返す?」
「俺はどっちでもいい。選べ、アオ。おまえが決めろ。こいつらの行き先を」
アオは目を伏せた。
……いつもなら、こんなことで迷わなかった。人の死は抗えるものではない。自分たちが干渉できるものではない。
でも今回は、ふたりの想いが強すぎた。強すぎて、まだ迷いの中にいる。少しの干渉でゆらいでしまえるほどに。
光希が、ふと湊の顔を見た。
「なあ。湊。もしさ、どっちかが目を覚ましたら、どうする?」
「やだよ。約束だろ。目を覚ますならふたりじゃなきゃ。残していくなよ。終わるのも再開もふたりがいい」
「でもさ、目覚めたら──また、いろんなことがあるんだぜ?嫁もらえ、孫の顔が見たい、いつまでも友達と暮らすなんてー…って…。」
「……………いいよ。それでも」
湊がぼそりと言った。
「ふたりならいいよ。おまえのことが大好きだから、一緒に生きるのを選びたい」
「湊…。…… バカだな、心中しようなんて。…… このまま終わったら、もうおまえを抱きしめることさえできないのに」
その言葉が、アオの胸に深く刺さった。
「モモ」
「……ああ、わかってる。送り返すぞ」
モモが手をかざすと、ふたりの時間がゆっくりと巻き戻り始めた。
空が滲み、アスファルトが揺れ、街灯が遠ざかっていく。
光希がそこで最後に見たのは、湊の微笑みだった。
***
湊が先に目を覚ました。
光希の手を握っていた。涙が頬をつたっていた。
「──ただいま、光希」
光希も数時間後に目を開けた。
無機質な天井と、点滴の音。隣にいる湊の手のぬくもり。
ふたりは、しっかりと抱きしめ合った。
「一緒に生きよう」
***
月へ戻ったアオとモモは、静かな夜を迎えていた。
「……俺たちが、あんなふうに揺れるなんてな」
モモが、湯気の立つカップをアオに差し出す。
アオは笑った。
「ああいう幸せも、あるんだね」
「なにが幸せかなんて人それぞれ違うもんだ。俺は… いまおまえといられりゃそれで満足だぜ。居心地いいからな」
「……モモ」
「ん?」
「いつも、ありがとう」
モモは照れくさそうにそっぽを向いた。
その夜、ふたりの食卓には、月菜と豆のスープが並んだ。
特別なメニューではないけれど、アオにとってはとてもあたたかく感じた。
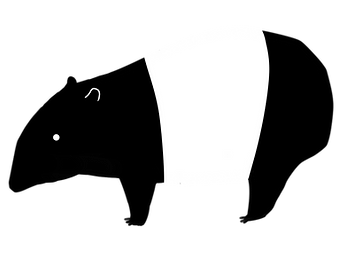
![[episode12]黒板消しの白い跡](https://static.wixstatic.com/media/114c79_8b62fd725c2141e3a392097f499edb6c~mv2.png/v1/fill/w_940,h_788,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_8b62fd725c2141e3a392097f499edb6c~mv2.png)







![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_298,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)
![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_74,h_62,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)





コメント