[episode15]悪夢を超えて
- mam

- 2025年8月4日
- 読了時間: 5分
目を閉じる前、凪人の最後の視界は――図書館の閲覧室の白い蛍光灯だった。
金曜の夜、いつも通り閉館準備をしていた。貸出端末を落とし、カウンターの明かりを落とし、書架の巡回を終えて戸締まりをする。 そのはずだった。
階段の踊り場に差しかかった瞬間、誰かの気配を感じた。 振り返る間もなく、喉元に鋭い熱が走り、何かが落ちる音がした。
それが、人生の終わりだった。
*
「……ここは?」
凪人は灰色の駅のホームにいた。 人気のないプラットホームに、電車の気配はない。風だけが吹き抜ける。
その場に、ふたりの来訪者が現れる。
ひとりは兎耳の少年、もうひとりは黒い毛並みの獏――そして、その獏は人の姿にも変わる青年だった。
アオとモモ。夢の番人。 死の直前、魂が揺らぐ一瞬にだけ訪れることができる、淡い境界の旅人。
「……君たちは、誰」
「君の最期の夢に来たんだ。君の“いちばん幸せだった記憶”を、探しに」
凪人はまばたきもせずアオを見た。
「そんなもの、あるわけない。 ……あんなふうに、終わるくらいなら、何を信じたって無駄だった」
凪人の脳裏に浮かんでいるのは、図書館の常連客だった男の顔。
はじめはただの親切だった。話しかけられ、本を貸し借りし、天気の話をし、凪人はどこか“彼”に親しさを感じていた。
――そう、昔の親友に、どこか似ていた。
小学生のときからの親友、晴紀(はるき)。 誰よりも笑顔が優しくて、誰よりもまっすぐな人だった。
だけど、その親しさは歪んでいった。
“彼”は凪人の生活の細部を知っていた。 自宅の最寄駅を、休日の過ごし方を、通院履歴まで。
最初は「偶然だろう」と思った。 次に「もしかして、好かれている?」と思った。 そして、ある日、図書館のカウンターに、見覚えのない“贈り物”を見つけた。
中身は、書き殴られた自分宛の手紙。ラブレターなどという甘いものではない。好意がどこかで反転したであろう、呪いのような言葉の数々。すぐに警察に…と思ったが、足がすくんで動けない。
そのうちに、背後から異質な気配を感じた。
「こんなに、好きなのに」
声の主は紛れもなく、“彼”だ。
怖くて、でも、信じたくて――逃げられなかった。
刃物が振るわれた時、凪人は「どうして?」という言葉しか出なかった。
*
「モモ、どうしよう。今の彼の心から、幸せな記憶なんて……」
「…………いや、ある」
モモは、静かに凪人の足元へと歩み寄る。 黒い獏の姿から、人の姿に変わり、ゆっくりと凪人の隣にしゃがみ込んだ。
「眠ってる記憶の奥に、いる。 “あの人”……晴紀って名前の、あんたの親友」
凪人がはっとする。
「……どうして、それを」
「俺は夢を喰うバクだからな。悪夢の奥の、君の心の核に眠ってるものを感じた」
モモは両の手を広げ、目を閉じる。黒い靄のようなものが凪人の足元から立ちのぼり、モモの指先へと吸い込まれていく。
その瞬間、凪人の身体がふるりと震えた。
「……なに、を……」
「あんたの悪夢を、一部だけ喰ったんだ。深く染みついた恐怖や怒りに覆われて、記憶の扉が見えなくなってた。だから俺が、少しだけ“片付けた”。アオにはできないけど、俺にはできることだ」
その言葉に、アオは目を見開いた。
「モモって……そんなこともできたんだ。知らなかった」
「まあな。でも、やたらにはやらない。記憶は、その人の心そのものだからな。食うなら、覚悟をもってだ。下手すると壊しかねない」
モモが手をかざす。 ホームの風景がふわりと揺れて、場面が切り替わる。
それは、夕暮れの学校のグラウンドだった。
白線を引き終えた体育の授業後、ふたりの少年が倉庫裏で肩を並べて座っていた。 ひとりは今の凪人とそっくりな少年、そしてもうひとりは、明るい笑顔の晴紀。
「なあ、俺たち、大人になったら何してると思う?」
「んー、晴紀は、絶対先生とか向いてると思う。笑顔で全員にプリント配るやつ」
「おまえは?」
「……図書館とか、いいなって思ってる。静かなとこ、好きだし」
「お。おれ本借りにいく!」
小さな約束。ふたりだけの夢。 それは凪人の中にずっと残っていた、ささやかな、けれど確かな“幸せ”。
でも、凪人は涙をにじませてつぶやく。
「……それでも。 最後に信じかけた相手が、自分を刺したんだ。 俺があの日、彼に“似てる”なんて思わなければ……きっと、こんなふうには」
アオが、静かに首を振った。
「でも、その過去があったから、君は信じようとした。 それはきっと、間違いじゃなかった」
モモも、そっと凪人に微笑む。
「悲しみがあるから、幸せも輝くんだ。 あんたが信じた時間が、本物だったことに、変わりはない」
*
風景がまた変わる。
白い光が降り注ぐ草原の中、晴紀がこちらに手を振っている。 微笑みは変わらず、少年のまま。
記憶の中の晴紀はまぶしくて、ああ、こいつのこと、好きだったんだよな。
自分は決して、不幸じゃなかった。
大丈夫・・・
凪人は少しためらったのち、その手を取った。
「……ありがとう」
モモとアオの姿を、遠く振り返りながら、光のなかへと歩き出す。
*
静かな月の夜。 帰還したモモとアオが、湯気の立つ湯飲みを手に、ぽつりぽつりと話す。
「夢が、……深かったね。 でも、モモの力がなかったら、あの人、ずっと悪夢に囚われてたと思う」
モモは湯飲みに口をつけ、ひとつ息を吐く。
「……夢ってのは、面倒なもんだな。 でも俺は、喰えば喰うほど、愛おしくなるよ。悲しみすら、きっと誰かの証だ」
アオは静かにうなずく。
「……モモって、ほんとにすごいな。ぼくにはできないこと、たくさんできる」
「おまえがいるから、俺ができることもある」
ふたりは湯飲みを傾けながら、少しだけ黙った。
窓の外には、地上の青い星が遠くまたたいている。
夢を送り出す、遠い星。
「……ねえ、あの人、今ごろ晴紀くんと、何を話してるかな」
「さあな。でも、きっと笑ってる」
今日も、月の食卓には、小さな灯りがともっていた。
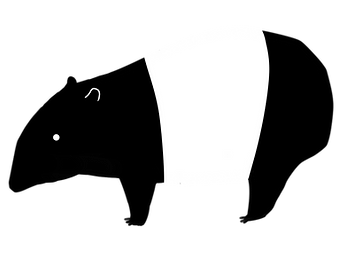
![[episode13]ふたりの部屋に灯りはともる](https://static.wixstatic.com/media/114c79_736ebb262d8a4d7695ed9c076f1f0930~mv2.png/v1/fill/w_940,h_788,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_736ebb262d8a4d7695ed9c076f1f0930~mv2.png)







![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_298,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)
![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_74,h_62,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)





コメント