[episode17]終わりじゃない旅路
- mam

- 2025年8月8日
- 読了時間: 4分
ホスピスの病室は、静かでやわらかな光に包まれていた。 カーテン越しに夏の日差しが差し込んで、白いリネンを淡く照らしている。窓の外では蝉が鳴いていた。
柊 真澄(ひいらぎ ますみ)、四十歳。 彼は元・看護師だった。何人もの患者の最期に寄り添い、涙も、感謝の言葉も、たくさん受け取ってきた。 それでも、自分が“看取られる側”になる日が来るとは想像もしていなかった。しかも、まだまだ現役でも良い年齢で。
末期の病。
自分の体調を気遣う余裕などなく、早期発見は叶わなかった。 独り身で、両親はすでに他界している。見舞いに訪れる親戚も、友達も、恋人もいない。
看護の現場は天職だと思った。学生時代の友達と遊ぶ時間を確保することもなく、つまり患者以外の他人のことを考えるような環境ではなかったから、恋人などつくる考えもなかった。
ただ、一人だけ、入所してから毎日顔を出してくれる人物がいる。 このホスピスで働く看護師、朝比奈 陽翔(あさひな はると)。 真澄が看護師として勤めていた頃の後輩であり、いまは別の病院からこの施設へ異動してきていた。彼が自分と同じ現場にいたのは5年ほど前までだったか。
看護師としてのふたりの絆は、単なる先輩後輩の関係にとどまらなかった。
ある日の夜勤、急変した患者にふたりで対応したときのこと。
止まった心臓を前に、陽翔が手を震わせながら処置を続ける中、真澄は冷静に指示を出した。運悪く医師が不在の時間帯で、ちょうど他の看護師は別音患者の対応に追われていた。事前に患者の状態の共有はされていたし、いざという時の対応も指導されていたからふたりで共にその患者の最期の時を迎えることになった。
その後、陽翔がぽつりと漏らした。
「……もし、先輩がいなかったら、俺、壊れてたかもしれません。まだ手が震えてる…」
「俺たちはそういう現場にいるんだからな。…でも、よくやったよ」
「先輩がいたからだよ。だから、俺は今もここにいられるんです」
これが初めてではない。何度も急変した患者の対応をふたりでした経験があった。
命の現場を共に越えた数々の記憶が、ふたりを結びつけていた。
だからこそ、陽翔は真澄を「看取る」と決めたのだ。
「先輩、起きてますかー」
「……おまえ、ほんとにヒマだな」
ややかすれた声で笑う真澄に、陽翔は椅子を持ってきていつものように腰を下ろす。
「ヒマじゃないですよ、ちゃんと勤務中です。わざわざ手ぇ空けてきてるんです」
「仕事しろ、仕事」
「サボりでもなんでも、俺は先輩の“最期を看取る係”って決めてるんで」
「勝手に決めるな」
でも――本当は、ありがたかった。 陽翔は明るくて、気遣いができて、患者からも職員からも好かれる男だった。 彼の隣にいると、世界が少し軽くなるような気がする。
ふと思い出す。 病院勤めの頃、夜勤の休憩中、陽翔がコーヒーを差し出しながら真顔で尋ねてきたことがあった。
「先輩、担当した患者さんが亡くなる時って、どんな気持ちになりますか?」
『輪廻転生があるとしたら、また会いたいって思うかな。なにか縁があると思う』
それほど深く考えず、希望もこめて冗談みたいに言ったつもりだった。
でも、あいつ、覚えてたんだな。
*
眠りの淵で、真澄はふたりの気配を感じた。
ひとりは兎耳の少年、アオ。もうひとりは夢喰いの獏、モモ。
アオがやわらかく微笑んで言う。
「はじめまして僕たちは、夢の案内人です。もうすぐ旅立たれるあなたの、“いちばん幸せだった記憶”を探しに来ました」
真澄はゆっくりと頷いた。痛みも重さもなく、ただ心がすこし澄んでいる。
「いちばん……ああ、それなら看護師の頃のことだな、きっと」
アオとモモは、そっと夢の記憶をなぞっていく。
*
病院のナースステーション。 真澄と陽翔が、夜勤明けの朝を迎えていた。
「なぁ、先輩。俺たち、忙しすぎて彼女できないよねぇ。どっちもこのまま彼女できなかったらさ、一緒に暮らすってどうすか」
「なにそれ」
「え、今すぐじゃなくて先の話だけど、俺、けっこう本気です。そんで引退したら余生をふたりでのんびり過ごそうよ」
そのときは笑いながら流したけれど、 心のどこかに、それを受け入れたいと思った自分がいたことも思い出した。
でも、恋愛感情なんて口にできる関係じゃなかった。 命の現場で、信頼と責任の積み重ねだった。 そしてそれでも――いま思えば、あれはたしかに、信頼の上にある恋慕だった。
*
夢の終わり、再び現れるふたりの案内人。
「準備は、できましたか?」とアオが問いかける。
真澄は、病室で交わした陽翔の最期の言葉を思い出す。
『またいつか会えたら、俺の恋人になってよ、先輩』
――まったく、おまえってやつは。
でも、あいつの声、ちゃんと届いてた。
「……うん。また、どこかで」
静かに目を閉じて、真澄は旅立った。 もう、寂しくはなかった。
*
月の庵。
アオとモモが、湯気の立つ茶碗を前に座っている。
「静かな記憶だったね」
モモがぽつりと言った。
「“また会いたい”って願う気持ち、…届いただろうさ」
アオはにこりと微笑んだ。
「うん。僕たちは、それを信じて見送るんだ」
ほのかな灯りの中、ふたりは静かに紅茶をいただく。
今日もまた、ひとつの夢がやさしく終わった。
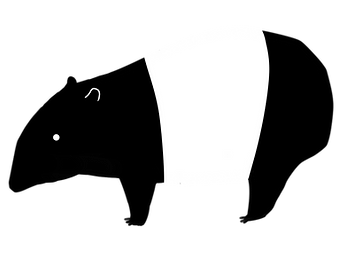
![[episode16]忘却の白い闇](https://static.wixstatic.com/media/114c79_6d31ac375cb84e858241a74acf29d86f~mv2.png/v1/fill/w_940,h_788,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_6d31ac375cb84e858241a74acf29d86f~mv2.png)







![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_298,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)
![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_74,h_62,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)





コメント