[episode19]愛して。
- mam

- 2025年8月15日
- 読了時間: 4分
底なしの沼みたいな、夜を生きていた。
一度足を踏み入れたら、抜け出すことなんてできない。
25歳の晴真(はるま)は、もう長いことその沼に沈んでいた。
安いホテルの一室、男の匂いと煙草の煙。
ポケットに入るだけの金をもらって、そのまま次の相手を探す。
そんな日々の繰り返しだった。
──これでいい。
自分なんて、どうせ誰かに大切にされるような価値のある人間じゃない。
だったら、誰かに愛されたいなんて思うこと自体、間違いだ。
そう思っていたのに、その夜、行きずりの男に飲まされた薬は、笑えるくらい甘く危険だった。
喉を通した瞬間、体は軽く、頭は遠く。
わけのわからない熱と衝動、目の前に誰がいて自分がどうなっているのかもわからない。
激しく溶けるような感覚と、いくら求めても満たされることのない感覚。不安、絶望、自分が自分じゃなくなる恐怖。
その最中に、ぷつりと意識が途切れた。
あとは暗闇。
ああ、やはり自分が消えても世界に何の影響もない。
暗闇しかない。
*
気がつくと、空気が柔らかく揺れる場所にいた。
夢の中──なのだと、直感した。現実ではない。
足元の石畳も、昼下がりの校舎も、どこか現実よりも淡く見える。
「……校舎??ああ、ここ、……大学じゃないか」
そう呟いた晴真の隣に、兎耳の少年・アオが立っていた。
彼は薄く笑って首を傾げる。
「この景色、きみの大事な記憶だよ。探してるんでしょ?」
歩き出すと、視界の先に黒縁眼鏡の男がいた。
北条。大学で哲学を教えていた教員。
彼は静かに本を閉じ、こちらを見て微笑む。
──ああ、この人だ。
晴真がずっと、片想いをしていた相手。
高校生のあたりから、自分は同性愛者であることを自認していた。
しかしだからと言ってまともに恋愛をしようと思えるほど自分を肯定していなかった。
誰にも気づかれないまま、記憶にも残らないまま生きて終わろうと思っていた。
両親とは不仲だし心をゆるせる友達もいない。
ただ、北条先生の講義だけは興味をもち、惹かれていった。
この人の講義の時間だけは、自分がひとりの大学生で生徒であることを感じられた。
彼はたくさんの生徒ひとりひとりに丁寧に接していた。
今どきこんなに情熱をもって指導してくれる先生もなかなかいないだろう。
「きみは勉強熱心だね。論文も読ませてもらったよ。
きみの文章は本当に伝えたいことをどこか控えてしまうような印象がある。
言いたいことが言えない、不器用なところがあるね」
そんな風に言って笑ってくれた。
ひとりでいても寂しくなかった。先生と顔を合わせられるならそれでよかった。
声も
表情も
優しくて芯があって、
自分はあり得ないようなことを幾度も妄想した。
彼に愛される方法はないだろうか
などと。
しかし、2年の後半には晴真がゲイだとどこかから噂がたち、大学を休みがちになった。
これ以上勉強をするのは無理だと悟り、中退を決めた。
最後と決めた日。
講義後の教室に残り、北条に話す機会をうかがっていたが、何度も口を開いては閉じた。
結局、最後まで言えなかった。
「大学を辞めることも言えなかったな。……好きだってことも」
アオは、少し切なそうに目を細めた。
北条はゆっくり近づいてきて、柔らかな声で言った。
「晴真くん、きみはずっと、自分を傷つける方を選んできたね。
でも……きみは、自分をもっと大切にしていいんだよ。
誰かに許されなくても、自分が許せばいい。」
その言葉が、胸の奥にじんわりと沁みていく。
哲学の授業で、北条がよく言っていたことを思い出す。
──人は、自分の存在を肯定することで、初めて自由になれる。
涙が溢れた。
ずっと、自分は愛されないと思っていた。
でも、それは自分が自分を愛していなかったからだ。
景色が少しずつ薄れていく。
最後に残ったのは、哲学書を片手に笑う北条の姿だった。
──自分をちゃんと愛せたらよかったな。そうしたら、先生に告白もできたかもしれない…
穏やかな光に包まれて、晴真は静かに目を閉じた。
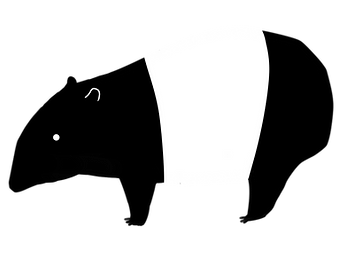
![[episode18]If You Could Hear Me Now](https://static.wixstatic.com/media/114c79_eb3c099e3e194f958757e0f943e136ff~mv2.png/v1/fill/w_940,h_788,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_eb3c099e3e194f958757e0f943e136ff~mv2.png)







![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_298,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)
![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_74,h_62,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)





コメント