[episode18]If You Could Hear Me Now
- mam

- 2025年8月9日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年8月21日
夜の街を、柔らかな風が抜けていく。
どこかのバーから漏れるギターの音と、誰かの笑い声。それらがゆるやかに溶け合って、遠くの空へ吸い込まれていった。
二十歳になったばかりの青年 ジェイミー・セラフィンは、その夜、交通事故に遭った。
音楽の道を夢見て、ギター一本で生きてきた彼は、ようやくプロとしての第一歩を踏み出そうとしていた矢先だった。
皮肉にも、その日が、デビューを控えた最終リハーサルの日だった。
目を閉じる。世界が闇に沈む。その深い沈黙の中に、ひとつの記憶だけが残っていた。
ギターを教えてくれた、近所のお兄さん――リアムの笑顔だった。
*
目を開けると、そこはどこか懐かしい街の片隅だった。
路地裏のレンガ塀。ポストの上に座る猫。灯りの落ちたカフェ。全部が、昔見た景色に見えた。
その真ん中に、白い耳をした少年――アオと、黒い髪を揺らす青年――モモが立っていた。
「ここは、あなたの夢。あなたがもうすぐ旅立つ前に、僕たちは“いちばん幸せだった記憶”を探しに来ました」
アオの言葉に、ジェイミーはきょとんと目を瞬かせた。
「……夢? 死ぬってこと? 俺が?」
モモが頷いた。
「でも、まだ終わってない。ちゃんと“気持ち”を伝えきれてないでしょ?」
「……………リアムに、だよね」
ジェイミーは、ぽつりと呟いた。
気持ちを向ける相手に、心当たりはひとりしかいない。
*
リアムは、五つ年上の隣人だった。
引っ込み思案だったジェイミーに、初めてギターを教えてくれた人。
彼の弾くアコースティックギターの音に、ジェイミーは一瞬で恋をした。
その音と、音の向こうにいるリアムの人柄に。
どれだけの歌を作っても、頭に浮かぶのはリアムの笑顔だった。
曲の主人公の想い人は、いつも彼だった。
「もしも君が僕を見つけてくれたら
恋に落ちてくれなくたっていい
ただ隣に座って 笑ってくれたら
それだけで、音楽は華やぐんだ
─ それだけで、僕は、幸せになれるんだ」
でも、現実にはその想いを告げられる機会はなかった。
これが「恋」だと気づいた頃には、彼はもう遠くの町で働き始めていて、会う機会も減っていた。
連絡先さえわからない。
代わりに、ジェイミーは彼への想いを忍ばせた楽曲を作り続けた。
恋をする想いを、歌に織り込んでいった。
切なさ、会いたい、伝えたい …
「届かなくたって構わない。君のそばにいたい」
そんなフレーズで奏でる楽曲は、オーディションの主催者の胸に響いた。
合格を言い渡されてすぐに感じたのは「もしリアムが自分の曲を聴いたら、想いが伝わるかもしれない」という希望だった。
けれど、
デビューを目前にして、その願いはかき消されてしまった。
*
「じゃあ、届けに行こうか」
アオが言った。
夢の中の街のカフェに、リアムが座っていた。少し歳を重ねた、でも変わらない優しい目。
「……久しぶり」
「やあ、ジェイミー。久しぶりだね」
「……夢の中だし、言ってもいいかな」
「ん?なにかあった?」
ジェイミーが、少し照れくさそうに笑う。
「ずっと、リアムのことが好きだった。ガキの頃から。音楽を続けたのも、全部あなたがいたからだよ」
リアムは、黙って彼の言葉を聞いていた。
そして、静かに返した。
「そうなんだね……ありがとう。君の歌を、聴かせてくれるかい?」
その言葉が、ジェイミーの心をやさしく夢を満たしていく。
ジェイミーの願いは、リアムに歌を届けることだったのだから。
*
月の庵に戻ったアオとモモ。
「音楽ってさ、すごいね」
アオがそっと呟くと、モモがにやりと笑う。
「今後、アオが好きそうな音楽を聴かせてやるよ」
「そうやってすぐ地上に行こうとする…モモが知ってる歌を歌って聴かせてよ」
「…… はは、そういう柄じゃねぇんだよなぁ」
その夜、ジェイミーの最期の歌が、誰かの心に静かに残っていった。
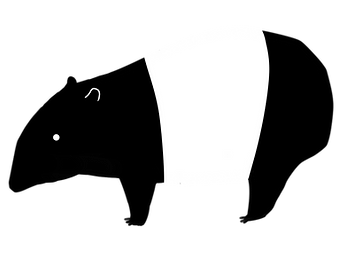
![[episode17]終わりじゃない旅路](https://static.wixstatic.com/media/114c79_a7a7c46c4906483b804761a397ffcca1~mv2.png/v1/fill/w_940,h_788,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_a7a7c46c4906483b804761a397ffcca1~mv2.png)







![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_298,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)
![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_74,h_62,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)





コメント