[episode21]廃墟の遊園地と最後の客
- mam

- 2025年8月20日
- 読了時間: 3分
地上へと降りたアオが最初に目を開けたとき、そこは闇に沈んだ遊園地だった。
折れた柵、剥がれたペンキ、風にきしむ観覧車。長く打ち捨てられた場所に、ひとりの老人が立っていた。
背を少し丸めた男は、フェンスに手をかけ、懐かしげに目を細めている。
春川——かつてこの遊園地で整備士として働いていた男だ。
「……久しぶりだな」
錆びついた観覧車を見上げて、春川は低く呟いた。
**
あれが、俺の最初の仕事だった。
まだ二十代、右も左も分からないころ。
そして——あいつに出会った。
回想の中で、若い春川が工具箱を抱えて立っている。
傍らには、快活に笑うひとりの男。名を健司といった。
「おい新人、ネジは締めすぎるなよ。鉄が泣いちまう」
「は、はいっ……!」
緊張でぎこちない春川の手を、健司は軽く押さえ、加減を教えてくれる。
夜遅くまで鉄骨に登り、汗を流し、工具を叩く日々。
二人で作った観覧車は、やがて街のシンボルになった。
点灯式の夜。
光が一斉に灯った瞬間、ふたりは誰にも言えない想いを分け合った。
——視線が合った。
自然と、手が触れた。
ただそれだけのことが、言葉より雄弁にすべてを伝えてしまった。
「この光は……俺たちの秘密だな」
健司が笑った。
春川は頷き、ただその手を離さなかった。
**
その後も、二人は表向きはただの同僚であり続けた。
しかし、作業場の奥にある古い工具棚の影で、ひそやかに言葉を交わした。
「今日も遅番か?」
「おう。終わったら……」
夜風が吹き抜ける園内の屋上で、缶コーヒーを分け合う。
誰もいない時間、隣に座り、肩が触れる。
それだけで胸が満ちる。
時には整備用の小屋で、油の匂いの中、手を重ねて眠った。
人に見せられない関係だからこそ、触れる瞬間のすべてが切実だった。
——「好きだ」と声にできなくても、互いに知っていた。
だが、時は容赦なく二人を引き裂いた。
健司は病にかかり、早くにこの世を去ってしまった。
休職という形で健司が現場を離れてからも、何度か病院に見舞いに行くことはできたが、健司の母親の前ではどうすることもできない。ろくに言葉も交わせないまま、あっというまに旅立った。
葬儀で春川は泣くことも許されず、ただ「同僚」として手を合わせた。
心の奥で「愛していた」と叫びながら。
それからずっと、観覧車は春川にとって「封じられた記憶」だった。
**
夢の闇に包まれた観覧車が、不意に瞬いた。
一つ、また一つ。
まるで記憶が呼び覚まされるように、錆びた骨組みに光が連なっていく。
「……健司」
春川の喉が震える。
ゴンドラがひとつ、音もなく開いた。
誘われるように乗り込むと、そこには——若き日の健司が座っていた。
「よぉ、春川」
あの日と変わらぬ笑顔。
観覧車がゆっくりと夜空に昇る。
そのわずかな時間に、二人は言葉を交わす。
「ずっと……言えなかった。俺は……お前が好きだった」
春川の声は震えていた。
健司は微笑んだまま、彼の手を取る。
「知ってたよ。俺もだ。最後に聞けて、うれしい」
手のひらに伝わる温もりは、夢だとわかっていても確かだった。
春川の目尻から、静かに涙がこぼれる。
頂点に達したとき、観覧車の光が夜空へと溶けていった。
健司の姿もまた、淡く消えていく。
だが春川の顔には、深い安らぎがあった。
「……やっと行けるね」
アオはつぶやき、小さく息を呑んだ。
隣でモモが静かに目を伏せる。
春川の魂は、静かに光の中へと溶けていった。
ふたりが去った後も、観覧車は一瞬だけ輝き続け、やがて闇に戻った。
——それは、最後まで二人だけの秘密の光だった。
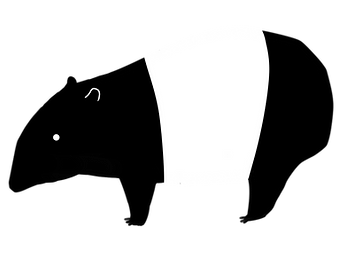
![[episode20]甘眠の密猟者 ― The Sweet Sleep Poacher ―](https://static.wixstatic.com/media/114c79_f8b2aac14dfe430cb99e261268814069~mv2.png/v1/fill/w_940,h_788,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_f8b2aac14dfe430cb99e261268814069~mv2.png)







![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_298,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)
![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_74,h_62,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)





コメント