[episode22] The Last Curtain Call
- mam

- 2025年8月22日
- 読了時間: 4分
体育館の天井は高く、夏の光がカーテンの隙間から差し込んでいた。
そこは夢の中――だが、19歳の秋人には、まるで昨日のことのように思えた。
高校の文化祭で使った体育館。舞台袖から眺めた景色は、憧れと緊張で胸を震わせた、あの日のままだった。
秋人は高校時代、演劇部に所属していた。だが文化祭直前、交通事故で大怪我を負い、舞台に立つ夢は叶わなかった。退院後も、公演前の舞台稽古には顔を出したが、本番の舞台に立てぬまま卒業した。外的な怪我は回復しても、舞台の上で演じるほどの体力は無くなってしまったし、病院には通う必要があったため稽古の時間を確保することもできなかった。
卒業して専門学校に進んだ今も、あの体育館の眩しさは、彼の心に残っていた。
いつか自分もあの舞台でスポットライトを浴びたいと願っていたし、演技を学ぶための進学も考えていたけれど、すべて諦めるしか選択肢がなかった。
そして
―もう命が長く続かないことを告げられていた。事故の後遺症が静かに、しかし確実に彼の身体を蝕んでいたからだ。医師は「まれにあること」と言った。色々と諦めた延長の流れでもあったため、本人も受け入れてはいたが、心の奥にはどうしようもない悔いが残っていた。
一度でいい、舞台に立ちたかった。
そんな願いに呼ばれるように、彼は夢の中で舞台袖に立っていた。
*
演劇部での記憶が蘇る。
高校に入学して興味のままに演劇部に入り、そこで好きになったのは、先輩の尚人だった。共学で女子も多くいたにも関わらず、いつでも目で追ってしまうのは先輩だった。
稽古場で台本を読む声が、秋人の胸を熱くした。
台詞を発するときの、少し低めで柔らかな声。その響きに、何度も救われた。
練習中、壁にぶち当たった時も、尚人は「大丈夫、お前ならやれるよ」と笑って肩を叩いてくれた。
肩を叩かれるだけで胸が熱くなった。
彼が舞台上で輝く場面を見るたび、その傍らで演じる他の部員への嫉妬と憧れが入り混じった。
気がつけば、どうしようもなく惹かれていた。告げられなかった想いは、ずっと心の奥にしまわれたままだった。
演じることの喜びも、仲間と笑う時間も、すべてが彼と一緒だったから輝いて見えた。
だが、そんな気持ちは伝えられなかった。ただの後輩でいた。
部室の喧騒の中でふと視線が合っても、気持ちがバレないようにと笑って誤魔化すしかできなかった。それでも、尚人の存在が、秋人の夢を燃やし続けた。
*
体育館の幕が開く。ざわめく観客席、光を反射するフローリング。秋人の胸は高鳴った。
袖の奥では、アオとモモが静かに見守っている。二人は客席からは見えない夢の案内人――秋人が最後の舞台を終えるのを導く存在だった。
秋人はそっと深呼吸した。目の前には当時の仲間たちが観客席に座っている。
照明係の友人が、緊張した顔でこちらを見つめている。
衣装を縫った後輩も、笑顔で両手を胸に合わせている。
そして――尚人の姿も。彼は変わらぬ眼差しで舞台を見つめていた。
モモが笑みを浮かべる。「ほら、やっと出番だぜ」
アオが優しく頷いた。
「きみはずっと舞台に立ちたかったんでしょう?行っておいで」
秋人は深呼吸し、舞台に一歩を踏み出した。
光の中で、観客席に尚人の姿が見えた。これは夢の中の幻だってことは分かっている。けれど、その笑顔は確かに自分を励ましていた。
独白をする舞台。
いつか先輩への気持ちを吐露するなら、舞台の上が良いと思っていた。
台本にあった台詞を発した瞬間、声が震えた。
次に出てきた言葉は、演技ではなく心の奥の叫びになった。
「……先輩。本当は、……俺、ずっとあなたが好きだった!一緒に演技をしたかった。隣に……いたかったです……」
体育館に響く声。観客が驚きに息を呑む。しかし尚人は、微笑んだまま拍手を送ってくれる。その音が胸に沁み、涙が視界をにじませた。
舞台が終わり、カーテンコールの拍手が鳴りやまぬ中、秋人は深々と頭を下げた。心に残っていた悔いが、溶けていくのを感じた。
*
幕が下り、暗がりに戻った舞台袖。秋人は静かに息をつき、目を閉じた。アオとモモがそっと近づく。
「どうだった?」とモモ。
秋人は微笑む。「うん。最高だった。やっと言えた!」
アオが囁く。「もう、後悔はないね」
秋人は小さく頷き、二人に導かれるように歩き出した。体育館の出口の向こう、柔らかな光が差し込んでいた。
最後にもう一度だけ、振り返る。そこには、尚人が立っていた。笑顔で手を振っている。その姿を胸に焼き付け、秋人は静かに微笑んだ。
そして光の中へ、足を進めた。
夢は静かに幕を閉じた。彼の舞台はここで終わる。
でも、悔やんだ気持ちは消えていた。
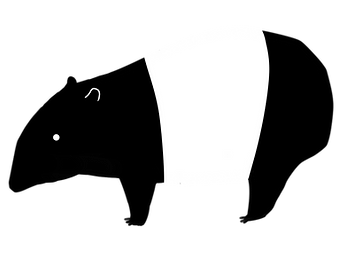








![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_298,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)
![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_74,h_62,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)





コメント