[episode30]君を迎える夜
- mam

- 2025年9月22日
- 読了時間: 3分
夏の夜の匂いが、夢の中に濃く漂っていた。湿った夜風に混じる線香花火の煙、屋台から流れる甘いソースの匂い。遠くで太鼓の音が響き、ちょうちんの光が並んで揺れている。
アオとモモは、並んでその光景を見つめていた。
今回の夢主は四十代半ばの男性。布団に横たわり、衰えた身体で呼吸を細く繰り返している。その魂が今、彼の「もっとも幸せだった記憶」の舞台に戻っている。
――夏祭りの夜。
そこに立つ夢主の前に、ひとりの男性が現れた。浴衣姿のまま、涼やかな笑みを浮かべて。
すでに亡くなって久しい、彼のかつての恋人。
「……来てくれたんだな」
夢主の声は、驚きよりも安堵に揺れていた。
「約束しただろ。ずっと、待ってるって」
男は、夜風の中でやわらかに笑った。
二人はかつて、互いの気持ちを確かめ合っていた。けれど、それを公にすることはなかった。肩を寄せ合うのは、誰もいない路地裏や祭りの雑踏の中だけ。人目に隠れて交わす視線と手のぬくもりが、唯一の真実だった。
若さゆえの情熱はあった。だが時を重ねるうちに、仕事や家庭、互いの事情が絡み合い、距離は少しずつ離れていった。
そしてある日、夢主は風の噂で彼の訃報を耳にした。
それからずっと、思っていたのだ。
――自分もその時が来たら、また会えるのだろうか、と。
祭囃子に包まれながら、二人は並んで歩いた。提灯の光に照らされた顔は、若い頃のままだ。時間に閉ざされた姿で、そこに立っている。
「おまえが死んだって聞いた時、どうして俺は駆けつけなかったんだろうって、ずっと悔やんでた」
夢主は苦笑した。
「でも、こうしてまた会えたじゃないか。……よかった」
「ああ。生きている間にできなかったことを、今からやれば良い。こうして手を繋ぐことだって、今なら」
男は軽やかに言って、そっと夢主の手を握った。その温もりは、あたたかかった。懐かしい体温を感じる。肉体を失ったはずなのに、触れ合う温度はあの頃のままだ。
二人の姿が、やがて灯籠の明かりの中に溶けていく。
遠ざかる背中を見つめながら、アオが小さく息をのんだ。
「不思議。……魂になっても……人は惹かれ合うんだね」
その横で、モモが肩をすくめる。
「まあ、そういうもんじゃないの。肉体だろうが魂だろうが、結局は“そばにいたい”って気持ちが先に立つ」
アオはしばらく黙って、祭りの灯を見送った。
やがて目を細めて、ぽつりとつぶやく。
「……なんだかそれって、僕たちにも少し似てるのかな…」
モモは苦笑した。
「おいおい、……けど、まぁ、嫌いじゃない表現だ」
夏の夜風が吹き抜け、屋台の灯がひとつ、ふっと消えた。
残された静けさの中で、二人はただ黙って立ち尽くし、旅立っていった魂の行方を見守っていた。
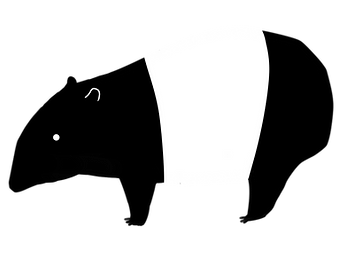
![[episode29]閑話・愛についての雑談](https://static.wixstatic.com/media/114c79_4ff459b96d444d888eb203a7b8052a70~mv2.jpg/v1/fill/w_940,h_788,al_c,q_85,enc_avif,quality_auto/114c79_4ff459b96d444d888eb203a7b8052a70~mv2.jpg)







![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_298,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)
![[episode36]幸せな記憶のために](https://static.wixstatic.com/media/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.jpg/v1/fill/w_74,h_62,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_17c52ef639b5419fa31f8cc732c7866d~mv2.webp)





コメント