[episode31]双つの命と彼岸花
- mam

- 9月25日
- 読了時間: 3分
白い天井をぼんやりと見つめながら、肺の奥に溜まった空気をゆっくり吐き出した。
秋分の夜。病室の窓から射す月の光が、点滴の管を淡く照らしている。
胸の奥が痛む。命が削れていく感覚が、もう恐怖ではなく淡い諦めとして身体に馴染んでいた。
——七歳で亡くなった弟のことを、男は思った。
自分と同じ日に生まれ、同じ顔を持ちながら、先に旅立った小さな命。
あの子を失ってから30年あまりの月日が流れたが、自分の半身を切り離されたような喪失感が拭えず、幼少期から今にいたるまで、誰かを愛することも未来を描くこともできなかった。
ただ生きていた。
心配してくれる友達でさえも、心の奥までは入れなかった。
そして病気を患ってからは、やっと終わるんだという喜びさえもあった。
「お前は死ぬ時、どんな気持ちだったんだろう」
何度も胸の内で弟に問いかけながら、今日まで生きてきた。
瞼が重くなる。
月明かりがぼやけ、世界が静かに遠ざかっていった——。
***
風が頬を撫でた。
目を開けると、そこは川辺の土手だった。満月が水面を白く染め、ススキが風に揺れている。
あの日、弟と虫取りをした懐かしい場所だ。
夜の空気はひんやりとして、赤い彼岸花だけが燃えるように咲き誇っていた。
その花畑の中央に、七歳の弟が立っていた。
小さな手を振り、無邪気な笑顔を見せている。
「やっと来たね、兄ちゃん」
男は立ち尽くした。自分は大人の姿だ。
声を絞り出す。
「……お前、ほんとうに……」
「うん。兄ちゃんを迎えに来たんだよ」
幼い弟は走り寄り、月光を浴びながら隣に並んだ。
歩き出すと、草の匂いと、幼い日の記憶が胸に押し寄せてくる。
「お前がいなくなってから、誰も好きになれなかった」
男は空を仰いだ。
「俺の半分が、お前だったから。残りの半分じゃ、誰も愛せなかった」
弟は柔らかく笑う。
「ぼくもさびしかったよ。でもね、兄ちゃんが見ていた景色、ちゃんとぼくにも届いてた。ぼくの分まで、いままで生きてくれて、ありがとう」
弟が手を差し出す。
「もうこっちに来ていいんだよ。今度こそ一緒に月を見よう」
迷いはなかった。
その手を取った瞬間、男の身体は淡い光に包まれ、背が縮み、指が小さくなっていく。
気づけば、同じ七歳の姿で弟と向かい合っていた。
誰が見ても双子だとわかるだろう。一卵性の双生児だ。
「また双子になれるかな」
「うん!また一緒に降りようね」
二人は笑い合い、手を握り合って駆け出した。
月夜に揺れる彼岸花の道を、少年の足で。
***
少し離れた堤防の上。
アオとモモが静かにその光景を見守っていた。
月の光に包まれ、双子の輪郭はやがて霞んでいく。
「魂って、家族って、肉体がなくなっても惹かれ合うんだね。」
アオが小さく呟く。
「生まれる前から、ひとつだったんだ。双子ならなおさらだろ。探す必要もなく迎えにきてるんだもんな。無駄足だったな」
別にいいけど、と、モモが耳を揺らして続けた。
アオは夜空を仰ぎ、満ちる月にそっと微笑んだ。
「ふたりでひとつ」という言葉が、胸の奥で静かに響く。
風に揺れるススキが、優しい音を立てていた。
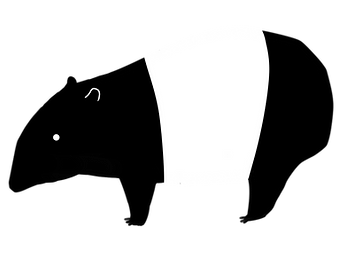
![[episode30]君を迎える夜](https://static.wixstatic.com/media/114c79_b8cd9409c62b442b8a2960e4ade896c5~mv2.jpg/v1/fill/w_940,h_788,al_c,q_85,enc_avif,quality_auto/114c79_b8cd9409c62b442b8a2960e4ade896c5~mv2.jpg)







![[episode31]双つの命と彼岸花](https://static.wixstatic.com/media/114c79_104954b917334c9d9a7af5d5c013291c~mv2.jpg/v1/fill/w_298,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/114c79_104954b917334c9d9a7af5d5c013291c~mv2.webp)
![[episode31]双つの命と彼岸花](https://static.wixstatic.com/media/114c79_104954b917334c9d9a7af5d5c013291c~mv2.jpg/v1/fill/w_74,h_62,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/114c79_104954b917334c9d9a7af5d5c013291c~mv2.webp)





コメント